Hi-Stat Vox No.24(2012年8月20日)
所得者上位1%の富裕層への課税:なぜ最高税率は80%以上でもいいのか?
Thomas Piketty (Paris School of Economics and CEPR)
Emmanuel Saez (University of California, Berkeley)
Stefanie Stantcheva (Massachusetts Institute of Technology)

米国における所得者上位1パーセントは、今では40年前に比べてはるかに高い国全体の所得シェアを占めている。このコラムでは、OECD加盟国18ヶ国を分析して、富裕層への低い課税が生産性と経済成長を高めるという主張に対して反論している。つまり、富裕層の最適な最高税率は80パーセント以上でも大丈夫で、超富裕層を除いて誰も不利益を被らない。
米国において税引き前総所得の上位1パーセントのシェアは、1970年代の10パーセントから今日では20パーセント以上に倍増している。(CBO 2011; Piketty and Saez 2003)同じような傾向は英語圏の他の国でも当てはまる。しかしグローバル化や技術革新が富の集中を加速させたと一般的に広く信じられているが、それらは原因ではない。なぜならヨーロッパ大陸の国々や日本などその他のOECD加盟国では、超富裕層の所得集中はかなり低いからである(World Top Incomes Database 2011)。
一方、上位所得者に対する所得税の最高税率は1970年代以降多くのOECD加盟国で大きく減少してきており、英語圏の国々では特に著しい。例えば、米国やイギリスにおける所得税の最高限界税率は1970年代に70パーセント以上もあったのが、レーガンやサッチャー改革以降は10年間以内に40パーセント分も大胆に削減された。
多くのOECD加盟国で大きな財政赤字や債務負担が問題となる時代において、政府が高額所得者の税負担を大きくすべきか否かは、重要な公共政策の課題であり、そのことによる潜在的な税収入の増加は非常に大きい。例えば、上位1パーセントの所得者層に属する平均的な米国人の所得税率を、現行の22.5パーセントから45パーセントに倍増すると、税収入は年間GDPの2.7パーセント分も増加する。1この額はブッシュ政権の減税政策をすべて廃止することに匹敵する。しかしもちろんこの単純な計算は静学的で、こうした大幅な増税の影響は、富裕層の経済行動や彼らが申告する税引き前所得、そしてより広範な経済に及ぶ可能性があり、最終的に徴収される税収も変わるかもしれない。最近の研究(Piketty et al. 2011)で、こうした問題を理論的・実証的に分析して、1970年代以降の富裕層の所得と最高税率に関して国際的な実証結果を示した1。
図1. 1970年代以降の上位1パーセント税引き前所得と最高限界税率の変化
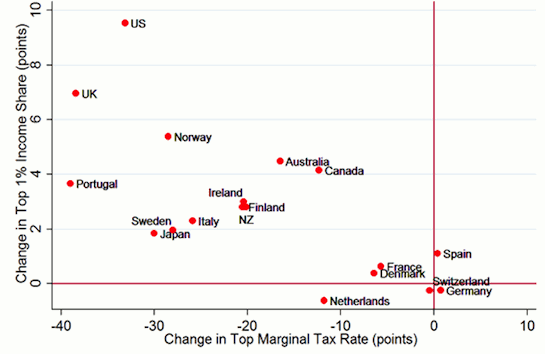
注:図では、OECD加盟国18ヶ国において1975-9年から2004-8年の間に起こった所得税最高限界税率の変化に対して上位1パーセント税引き前所得シェアの変化を示している。(最高税率には国・地方の個人所得税が共に含まれる。World Top Income Databaseのデータ利用可能性のため、厳密な年次は国によって若干異なる。
出所:Piketty et al. (2011), 図4A
富裕層の所得シェア情報が利用できるOECD加盟国18ヶ国について分析した図1を見ると、最高税率の減少は上位1パーセントの税引き前所得シェアが1975-79年から2004-08年に増加したのと確かに強く相関している。例えば、米国において所得税の最高税率は35パーセント減少して、上位1パーセントの税引き前所得シェアは10パーセントも非常に大きく増加した。対照的に、同時期のフランスやドイツにおいて、最高税率も上位1パーセントの税引き前所得シェアもほとんど変化していない。従って、最高税率の変遷は税引き前所得の集中を予測するのに適している。最高税率に所得上位層の税引き前所得が強く関連しているのを説明するシナリオは三つあり、それぞれ非常に異なった政策的インプリケーションを示唆し、またデータで検証することができる。
第一に、最高税率をもっと引き上げると、極めて有能な労働者は仕事に対する労力を減らし、新しくビジネスを創出するインセンティブを減らすかもしれない。いわゆる供給サイドの効果である。このシナリオでは、最高税率を下げることで、富裕層の経済活動がより活発になり、経済成長も促進される。図1で示された上位所得シェアと最高税率の相関がすべてこのような供給サイドの効果によるものだとしたら、税収を最大化する最高税率は57パーセントになる。この数字によると、米国において富裕層に対する課税を強める余地がまだ若干あるが、多くのヨーロッパ諸国ではすでに上限に達していることを示唆している。
第二に、最高税率の引き上げによって脱税が多くなる。このシナリオでは、脱税の機会や抜け道で穴が開いた税制において最高税率の引き上げは生産的ではない。しかし、より良い政策は、まず抜け穴を補修して脱税の機会を削減することで、それから最高税率を上げることである。十分な政治的意思と課税を実施する国際的な協力があれば、広く知られ確認されている多くの脱税の機会を減らすことができる。深刻な脱税の余地を許さない幅広い課税ベースであれば、非生産的にならない程度に高い最高税率を設定する範囲は、供給サイドの現実的対応のみが制約となるであろう。
第三に、標準的な経済モデルでは賃金が生産性を反映すると仮定されているが、こうした仮定を疑う大きな理由はいくつもある。特に、所得分布の上位を占める経営者たちは、複雑な組織で働いているためその実際的な経済的貢献を計測することが非常に難しい。こうしたシナリオでは、所得上位層は賃金交渉に傾注して、また報酬委員会に働きかけて自分達の賃金を部分的に決めることができるかもしれない。当然のことながら、最高税率が低ければそうした“レントシーキング”のインセンティブはより強くなる。この場合、最高税率が削減されてもなお所得上位層の所得シェアが高まることがあり、図1で観察された傾向と整合的である。しかし今度は残り99パーセントを犠牲にして上位1パーセントの所得が増えることになる。言い換えると、最高税率の削減は上位層のレントシーキングを触発するが、全体的な経済成長に影響しない。供給サイドを重視する第一のシナリオと比べた時の重要な相違点である。
上記の様々なシナリオを識別するために、最高税率の削減がどれくらい経済成長を押し上げたのかを分析する必要がある。図2によると、最高税率の削減は1970年代以降の年間一人当たり実質GDP成長率の平均値と相関関係は見られない。例えば、イギリスや米国のように最高税率を大幅に削減した国は、そうしなかったドイツやデンマークなどの国に比較して、より高い経済成長を達成していない。従って、図1で確認された最高税率に対する税引き前所得上位層の変化は、生産的な労力の増加というよりも、大部分がレントシーキングの拡大によるものと言えそうである。
図2. 1970年代以降の一人当たりGDP成長率と最高限界税率
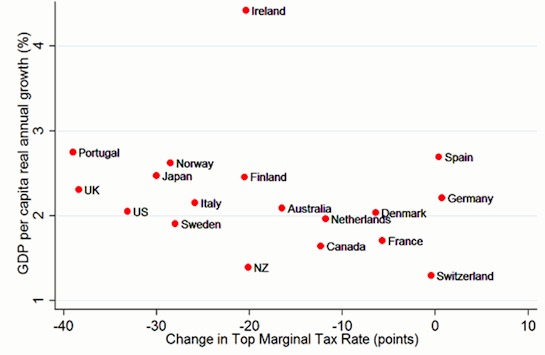
注:図では、1975-9年から2004-8年の間に起こった所得税最高限界税率の変化に対して一人当たりGDP成長率の平均が示されている。(厳密な年次は図1と同じで国によって若干異なる。)相関関係は実質的に無く、統計的に有意ではないため、最高税率の削減はより高い経済成長につながらないことを示唆している。
出所:Piketty et al. (2011), 図4B
当然のことながら、国際比較の結果は頑健ではなく正確な結果はモデルや年次、また国のサンプルなどによって変わる。しかしながら概して肝心なのは、高所得国は大きく異なる税制政策を実施してきたにも関わらず、過去30年間の間すべてほぼ一様に成長してきている点である。経済モデルにおいて、最高税率が削減された時に上位所得者の反応の一部はレントシーキングの拡大と生産的な仕事の増加になることを仮定し、推定したモデルのパラメーターから中間的な値を導いた。その結果、最高税率は最大で83パーセントの高さまで設定できる可能性が明らかとなった。一方、純粋な供給サイドを考慮したモデルでは、57パーセントであった。
1970年代まで政策担当者や世論は、最上位の所得階層にとって賃金上昇は生産的な労働意欲というよりは強欲や他の社会的に無駄な活動を映しているにすぎないと、善かれ悪しかれおそらく考えていたのであろう。それが理由で、米国やイギリスにおいて限界税率を80パーセントの高さにまで設定できたと言える。レーガンやサッチャー改革によって、それ以降こうした高い最高税率は考えられない数字となった。しかし、所得集中が進むにつれ1970年代以降の経済成長は数十年間停滞し、金融部門の横暴が世界同時不況を引き起こしたことで、レーガン・サッチャー改革の再考がおそらく進んでいるのだろう。イギリスにおいて上位所得者の極端に高い所得を削減することを一部の目的として、2010年に所得税の最高税率は40パーセントから50パーセントに引き上げられた。米国においても、ウォールストリートを占拠する抗議活動や“我々は残りの99パーセント”という有名なスローガンは、残りの99パーセントは犠牲にして上位1パーセントが得をするという見方を反映している。
結局、上位層の所得は生産性を十分反映しているか、もしくはレントシーキングの結果を反映しているのか、一般世論の見方によって将来の最高税率は決まってくる。所得の集中が高まることで上位所得者が活用できる経済資源は増えるため、彼らは(シンクタンクやメディアにより)社会通念や(ロビー活動により)政策に影響力を強めることができる。その結果、所得不平等が一般世論に、そして政策に影響を与える一定の逆の因果関係が生まれる。我々経済学者の仕事として、こうした考え方に対して、説得力を持った理論的・実証的分析により少しでも光が当てられることを望んでいる。
注釈
1. 本計算では上位1パーセントの所得シェアが20パーセントだと仮定している。上位1パーセントの所得シェアは2007年の23.5パーセントをピークとして、景気の谷となった2008年は21パーセントに、2009年は18パーセントに減少した。2010年と2011年は、上位1パーセントの所得シェアは再び20パーセントまで上昇すると予測される。課税目的で報告された総市場所得は、1999年から2008年の平均で見るとGDPの約60パーセントである。従って、上位1パーセントの平均税率を22.5パーセント増加すると、GDPの2.7パーセント(=0.6×0.225×0.2)と等しくなる。もしくは、2011年時点のGDPが15兆ドルなので、4050億ドルとなる。
参考文献
Congressional Budget Office (2011), “Trends in the Distribution of Household Income Between 1979 and 2007”, US government Printing Press: Washington DC.
Piketty, Thomas and Emmanuel Saez (2003), “Income Inequality in the United States, 1913-1998”, Quarterly Journal of Economics, 118(1):1-39, series updated to 2008 in July 2010, online at http://elsa.berkeley.edu/~saez/
Piketty, Thomas, Emmanuel Saez, and Stefanie Stantcheva (2011), “Optimal Taxation of Top Labor Incomes: A Tale of Three Elasticities”, CEPR Discussion Paper 8675, December.
The World Top Incomes Database (F Alvaredo, T Atkinson, T Piketty, and E Saez).
翻訳:COE特別研究員 田中清泰